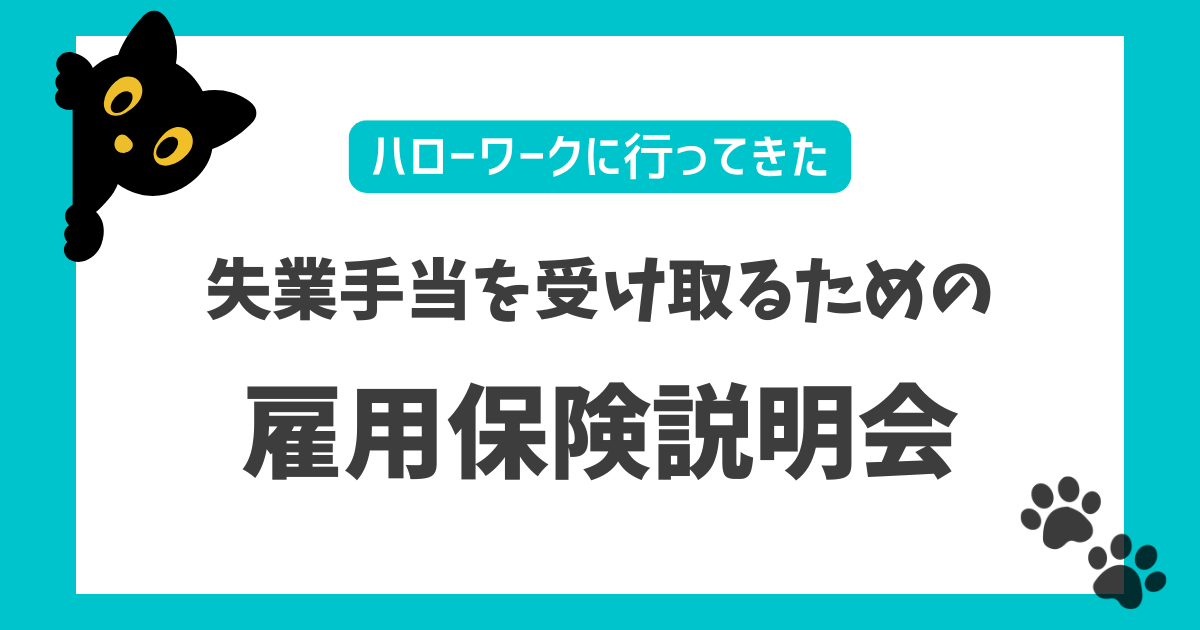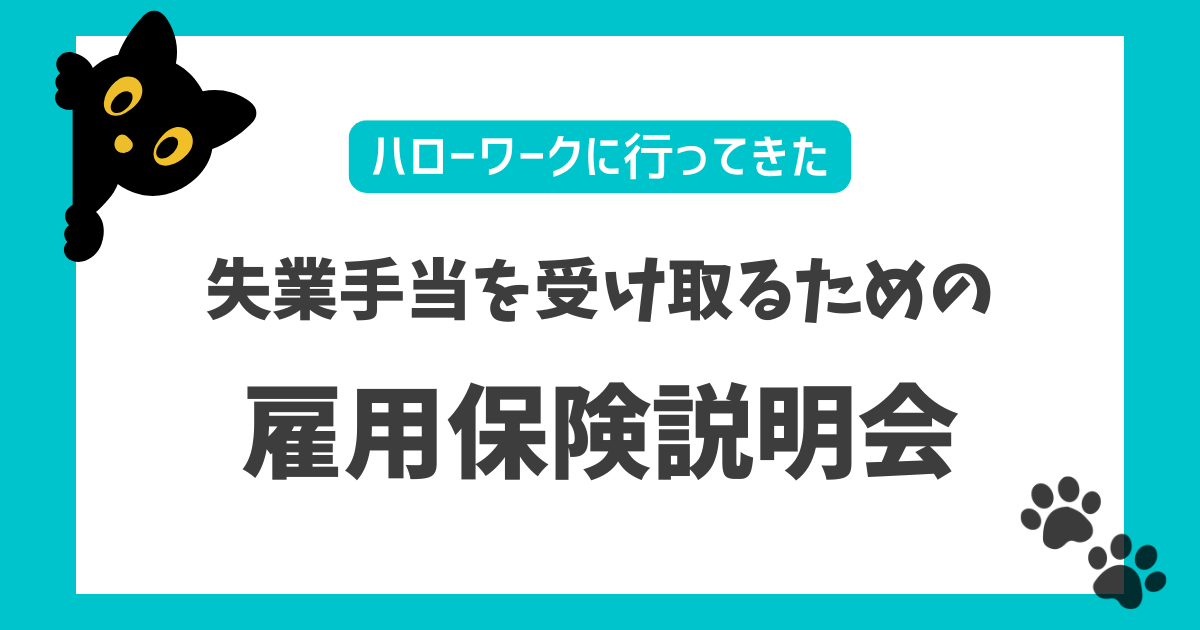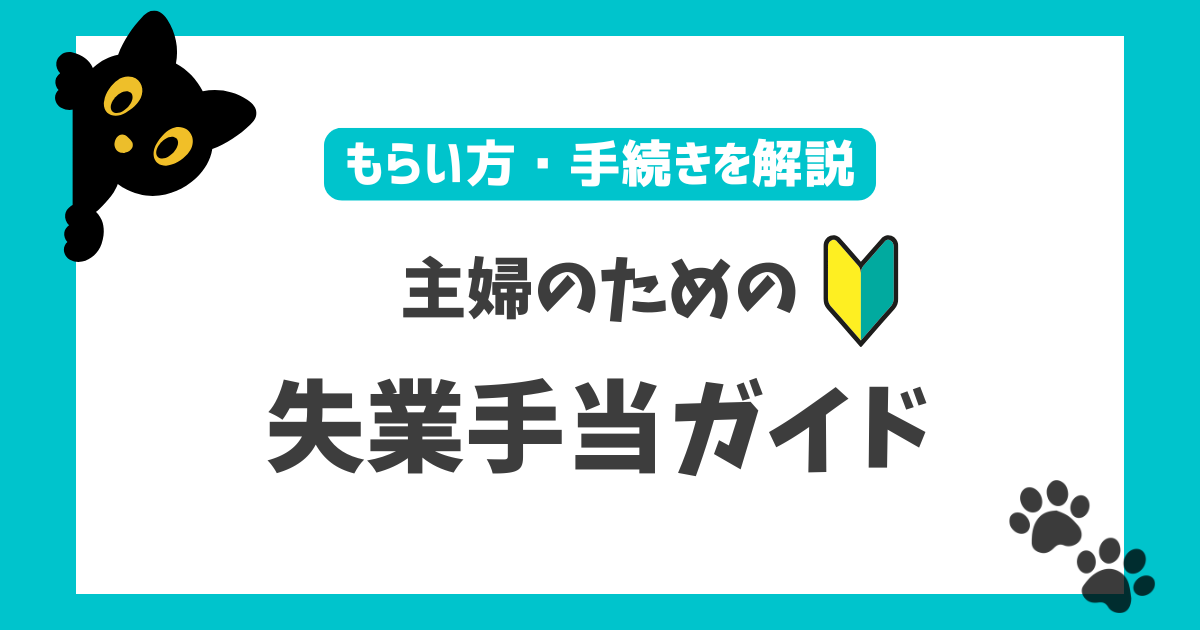- 退職後の生活費が不安で、この先どうなるのか心配
- 主婦でも失業手当がもらえるのか、制度がいまいちわからない
- ハローワークに行く前に、最低限の知識だけでも知っておきたい
そんな気持ちを抱えながら、情報を探している方へ。
失業手当は「働く意思があり、条件を満たせば主婦でも受け取れる制度」です。
でも、仕組みが複雑で、何から始めればいいかわからないまま時間が過ぎてしまう人も多いのが現実です。
私自身も、派遣で働いたあと退職し、いまちょうどハローワークで失業手当の手続きを進めているところです。
はじめてではないものの、制度や流れが以前と変わっていて、確認しながらでないと不安になる場面も多くあります。
この記事では、「主婦が失業手当をもらうために知っておくべきこと」を、制度の基本・手続きの流れ・注意点まで必要な情報だけに絞ってわかりやすく解説します。
制度を知って行動すれば、無駄な出費や手続きミスを防げて、安心して次の一歩を踏み出せます。
 はないろ
はないろまずは知ることが、いちばんの備えです。
まずは知っておきたい基礎知識|「失業の状態」とは?【予備知識】
失業手当を受け取るには、単に仕事を辞めただけでは足りません。
「失業の状態」とハローワークに認められる必要があります。
「失業の状態」と認められる3つの条件
以下の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
- 働く意思がある
- すぐに働ける健康状態・生活環境にある
- 積極的に仕事を探しているのに職についていない
\ここがポイント!/



“辞めたからもらえる”ではなく、“働くつもりがある”が大前提です。
失業手当が受け取れない代表的なケース
次のような場合、失業の状態とは認められません。
- 妊娠・出産・育児のため、すぐに働けない
- 病気やケガで就職できない
- 退職後にしばらく専業主婦として休養する予定
- 親の介護などで働ける状況にない
- 家業(自営・農業など)を手伝っている
- 会社の役員に就任している
- すでに就職が決まっている(内定を含む)
- 学校に通っていて就職できない(昼間の学生など)
\勘違いしやすい!/



「子どもが小さいから、今は無理」では対象外になります。
再就職の意思と、すぐ働ける状況が必要です。
主婦は失業手当の対象?もらえる人・もらえない人の条件を解説
失業手当は、主婦でも条件を満たせば受け取れる制度です。
ただし、すべての主婦が対象になるわけではありません。
「もらえる人」と「もらえない人」の違いは、主に雇用保険への加入状況と再就職の意思にあります。
失業手当がもらえる条件
以下すべてに当てはまる場合、主婦でも失業手当の受給対象になります。
- 過去に雇用保険に加入していた(原則1年以上)
- 今すぐ働く意思があり、求職活動をしている
- 病気や妊娠、介護などで働けない状況ではない
\ここを確認!/



パートや派遣で働いていた場合でも、週20時間以上で雇用保険に加入していれば対象です。(原則1年以上)
雇用契約書や給与明細で「雇用保険料」が引かれているかを確認しましょう。
失業手当がもらえない主なパターン
以下に当てはまる場合は、失業手当の支給対象外になる可能性があります。
- 雇用保険に入っていなかった(週20時間未満など)
- 働く意思がなく、当面は専業主婦になるつもり
- 出産・育児・病気・介護などですぐに働けない
- すでに新しい職場が決まっている(内定を含む)
- 学業に専念している(昼間の学生など)
\要注意!/



「しばらく働かないつもり」や「扶養に入ってのんびりする」は失業手当の対象になりません。
ハローワークで“すぐ働ける状態”と認められることが大前提です。
失業手当はすぐにもらえない?|待期期間と給付制限の仕組み
失業手当(基本手当)は、ハローワークで手続きをしてもすぐには振り込まれません。
最初に「待期期間」があり、さらに「給付制限」があると、実際の支給は最大で2〜3か月後になることもあります。
以下で、それぞれの仕組みをわかりやすく解説します。
待期期間とは?【全員に共通】
失業手当の申請後、最初の7日間は支給が発生しない期間があります。
これを「待期期間」といいます。
- 対象:すべての人(自己都合・会社都合問わず)
- 期間:7日間
- カウント開始日:「受給資格決定日(=失業手当の申請手続きをした日)」



待期期間中は、バイトなどで1日でも働くとNG。
7日間ずっと何も働かず、収入がない状態を保つ必要があります。
給付制限とは?自己都合退職で待たされる仕組み
給付制限とは、自己都合で退職した場合に、失業手当の支給が一定期間「遅れる」仕組みです。
自己都合退職の場合、まず7日間の「待期期間」を過ごしたあとも、さらに2〜3ヶ月間の「給付制限期間」が続きます。
この間は、働いていなくても手当は支給されません。
給付制限期間の支給タイミング(退職理由別)
| 退職理由 | 給付制限 | 失業手当の支給時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 会社都合退職 | なし | 待期期間後すぐ | 倒産・解雇・契約終了など |
| 自己都合退職(一般) | あり(原則2か月、最大3か月) | 給付制限後の認定日から | 正当な理由なし |
| 正当な理由のある自己都合退職 | なし | 待期期間後すぐ | ハラスメント、介護、通勤困難など |
正当な理由が認められると?
たとえ自己都合退職であっても、以下のような事情があれば給付制限が免除されることがあります。
- パワハラ・セクハラ
- 過労・長時間労働
- 家族の介護
- 通勤困難(引っ越し・交通手段の廃止など)
- 妊娠・育児による退職 など
ハローワークの判断によるため、認められるかどうかはケースバイケースです。
診断書や通勤経路図などの証明書類を求められることがあります。
失業手当の申請手続きと流れを6ステップで解説【初めてでもわかる】
失業手当をもらうには、ハローワークでの手続きが必要です。
「何から始めればいいの?」「どれくらい時間がかかるの?」と不安に感じる方も多いですが、流れは決まっています。
ここでは、実際の流れを6つのステップに分けて、必要な書類や注意点もあわせて解説します。
STEP1:離職票を受け取る【ここがスタートライン】
失業手当の手続きは、まず「離職票」がないとはじまりません。
離職票とは?
- 会社を退職したことを証明する書類です。
- ハローワークで失業手当の申請をする際、必ず必要になります。
- 2種類あります
- 離職票-1:退職日や雇用保険の加入期間などが記載
- 離職票-2:退職理由や賃金の情報が記載(とても重要!)
いつ届く?
- 通常、退職から1〜2週間以内に会社から郵送されます。
- 会社が発行手続きをしていないと、送られてきません。
- 2週間を過ぎても届かない場合は、会社に確認を。
ここに注意!



「退職理由(自己都合 or 会社都合)」の記載内容がとても大事です!
内容によっては、支給までの期間が大きく変わることがあります。
もし記載に納得がいかない場合は、ハローワークで相談できます。
離職票がもらえないケース
パートなどの短期雇用では、「離職票は出せない」と言われることがあります。
ですが、雇用保険に加入していたなら、離職票は発行されるべきものです。
加入の有無が不明なときは、給与明細に「雇用保険料」が差し引かれているかを確認してみてください。
雇用保険に入っていたのに離職票が届かない場合は、勤務先に問い合わせて確認しましょう。
STEP2:ハローワークで失業の手続き【ここから失業手当がスタート】
離職票が届いたら、できるだけ早めにハローワークへ向かいましょう。
ここで失業手続きを済ませておかないと、失業手当のカウント(待期期間など)が始まりません。



私は、離職票が届いた翌日にハローワークへいきました
失業手当の手続きに必要な持ち物一覧
| 持ち物 | 内容・補足 |
|---|---|
| 離職票(1・2) | 原本が必要。これがないと手続きできません。 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードがあれば1枚でOK。 ない場合は運転免許証や健康保険証+補助書類などで対応可能。 |
| キャッシュカードまたは通帳 | 給付金の振込先口座を確認するために使用。 |
| 証明写真(3×2.5cm) | マイナンバーカードに写真があれば不要。なければ持参。 |
| 印鑑 | 念のため持参。最近は使わないケースも多い。 |



離職票・本人確認書類・口座情報は必須。
マイナンバーカードがあれば、写真や印鑑はなくても大丈夫でした!
当日の流れ
- 総合受付で番号札を取る
入口の案内に従い、番号札を取って総合受付へ。
「失業保険の申請」と伝えると、該当窓口に案内されます。
- 書類の確認・提出し、制度の説明を受ける(約20分)
指定された窓口で必要書類を提出し、失業手当の仕組みや今後の流れについて説明を受けます。
配布資料を使って口頭で丁寧に解説されます。
<提出書類の例>
・離職票(1・2)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・振込口座がわかるもの(キャッシュカードなど)
※マイナンバーカードがあれば、証明写真や印鑑は不要になることもあります。
- 職業相談(求職申込み)を行う(約30分)
勤務条件や希望職種などを職員がヒアリングしながら入力します。
この手続きを行うことで、ハローワークの求人に応募できるようになります。
→ この日が「受給資格決定日」となり、7日間の待期期間がスタートします。
遅れると支給日もそのぶん後ろ倒しになるので、できるだけ早めに手続きするのがおすすめです。
当日の注意点・よくある疑問
- 予約は不要
書類がそろっていれば、その日中に手続きが完了します。 - 待ち時間は長め
初回申請者と認定日で来ている人が同じ窓口なので、1時間以上かかることもあります。 - 証明写真は不要な場合も
写真付きのマイナンバーカードがあれば代用でき、提出不要になるケースがあります。 - 印鑑は不要なことが多い
ただし、書類に不備があった場合に備えて、念のため持参しておくと安心です。 - 服装や持ち物に指定はなし
スーツなどの堅苦しい服装は不要です。私服で問題ありません。



私は証明写真と印鑑を持っていきましたが、どちらも使いませんでした。マイナンバーカードがあると便利!
ポイントまとめ
- 書類がそろっていれば、予約なしでもその日のうちに完了できます
- 本人確認にマイナンバーカードを使うと手続きがラクに
- 離職票が届いたらすぐに行動を。求職申込みが遅れると、支給も後ろ倒しに
STEP3:雇用保険説明会に参加する【支給には必須】
STEP2の手続きのときに、「雇用保険説明会」の案内が渡されます。
実際の説明会は、STEP2の日から1〜2週間後に開催されるのが一般的です。



この説明会に参加しないと、失業手当の支給が始まりません。
必ず出席しましょう。
説明会の流れ(所要時間:約1時間半)
- 制度の概要説明(約20分)
- 動画視聴(約20分)
- 失業認定申告書の書き方説明(約40分)
配布された資料を見ながら進行するので、メモを取る準備をしておくと安心です。
実際の説明会の様子は、こちらの記事に詳しく書いています。
ハローワークの雇用保険説明会へ|失業手当と職業訓練の話も聞いてきた
会場の雰囲気と注意点
- 会場は役所の会議室のような雰囲気。
- 服装は自由。カジュアルでOKです。
- 冷房が強い場合もあるので、羽織ものがあると安心。
- 椅子と資料のみで机がないケースも。下敷きやクリップボードがあると便利。
ポイントまとめ
- 説明会の案内は、ハローワークでの初回手続き時にもらえます
- 開催は申込みから1〜2週間後が目安
- 失業手当を受け取るには参加が必須
STEP4:初回認定日|失業手当の受給が「決まる」日
初回認定日は、失業手当の支給が「決まる」大切な日。
ハローワークから指定された日時に出向きます。



日時は、STEP2で受け取った「失業認定申告書」に記載されています。
初回認定日の流れ
- 受付で「失業認定申告書」を提出する
あらかじめ記入しておいた申告書を窓口に提出します。
求職活動の内容や就職状況についての欄をしっかり埋めておきましょう。
- 雇用保険受給資格者証を受け取る
「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
この書類には失業手当の支給額や支給日数などが記載されており、今後の手続きでも必要になります。
次回以降の認定日にも必ず持参が必要なので、大切に保管しておきましょう。
- 窓口で職員と内容を確認
提出した申告書をもとに、職員の方から簡単な確認があります。
「どんな求職活動をしましたか?」など、申告内容とズレがないかを見てくれます。
特に問題がなければ、5〜10分ほどで終了します。
- 支給予定日の案内を受ける
認定が完了すると、失業手当の支給日について案内があります。
ただし、退職理由によって案内の有無が異なります。
・会社都合など給付制限がない場合
この場で振込予定日の案内あり。通常は認定日から数日〜1週間後に振込。
・自己都合など給付制限がある場合
この時点では振込予定日の案内はなし。制限期間(原則2カ月)終了後の認定日で、支給と振込日が決まる。
初回認定日のポイントと注意点
- 求職活動の実績は1回でOK
初回だけは、STEP3の「雇用保険説明会」への参加だけで実績としてカウントされます。
職業相談や求人応募など、別の活動は不要です。 - 無断欠席はNG
やむを得ず行けない場合は、必ず事前にハローワークへ連絡を。
無断で欠席すると、認定されず支給が受けられないこともあります。
STEP5:失業手当の振込を確認する【いよいよ支給スタート】
初回の振込タイミングは、「給付制限の有無」で変わります
失業手当の初回支給日は、退職理由によって異なります。
- 給付制限なし(会社都合など)の場合
初回認定日の数日〜1週間後に、指定口座へ振り込まれます。 - 給付制限あり(自己都合退職など)の場合
原則2カ月間の給付制限があり、その後の認定日を経てから振込となります。
※この間も求職活動実績を積み、認定日には出席が必要です。
支給される金額のしくみ
振り込まれる金額には、次のような条件が反映されます。
- 待期期間の7日間
支給されません - 給付制限がある場合(自己都合退職など)
原則2か月間は支給されません - 支給対象となるのは、初回認定日までのうち上記を除いた日数分です
実際の支給額や日数は、「雇用保険受給資格者証」に記載されています。
振込が確認できたら
失業手当は1回きりではありません。今後も継続して受給するには
- 次回の失業認定日に出席
- 求職活動実績を正しく記入して提出
この流れを繰り返すことで、次回以降の支給が継続されます。
STEP6:次回の認定日までに「求職活動実績」を積む
失業手当を継続して受け取るには、4週間ごとの「失業認定日」にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告する必要があります。
次回の認定日までにやることは、主に3つです
- 2回以上の求職活動実績をつくる
※2回目以降の認定日では「2回以上」が基本ルールです
(例:職業相談・求人応募・セミナー参加など) - 失業認定申告書に、実績の内容を記載しておく
- 指定された認定日にハローワークへ行き、書類を提出する
活動実績として認められるものの例
- ハローワークでの職業相談や求人紹介
- 求人への応募(書類提出・面接など)
- ハローワーク主催のセミナーや就職支援イベント
- 民間企業などが主催する説明会・ガイダンス
- 公共職業訓練の説明会参加 など



求職活動の実績が足りないと、その期間の失業手当は支給されません。
体調不良などで活動できない場合は、かならず事前にハローワークに相談を。無断で休むと認定されなくなることもあるので注意です。
失業手当はいくらもらえる?|計算方法と目安を解説
失業手当の金額は、人によって異なります。
「退職前の給与額」や「年齢」によって変わるため、あらかじめ目安を知っておくと安心です。
支給額の基本は「賃金日額×給付率」
失業手当の1日あたりの金額は、「賃金日額」に「給付率」をかけて計算されます。
- 賃金日額:退職前6か月の給与を元にした、1日あたりの平均賃金
- 給付率:50〜80%(賃金が低い人ほど高め)
パートや派遣などで月収が低かった人は、給付率が高くなる傾向があります。
年齢・離職理由によって支給期間も異なる
失業手当が支給される期間(所定給付日数)は、以下の2つで決まります。
- 離職時の年齢
- 雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)
自己都合退職よりも、会社都合退職のほうが長くもらえる傾向があります。
上限・下限額も決まっている
年齢ごとに、1日あたりの支給額には「上限」と「下限」があります。
たとえば、2025年度の上限額は以下のとおりです。
| 年齢 | 上限額(1日あたり) |
|---|---|
| ~29歳 | 約6,300円前後 |
| 30~44歳 | 約7,000円前後 |
| 45~59歳 | 約7,200円前後 |
| 60~64歳 | 約6,600円前後 |
※年度ごとに変わるため、最新情報は厚労省サイトやハローワークで確認を
月収20万円だった場合の失業手当の金額は?
試算例
- 月収
20万円 - 1日あたりの賃金日額(目安)
約6,667円(20万円 ÷ 30日で簡易計算) - 給付率
60%
↓
基本手当日額:6,667円 × 60% ≒ 約4,000円
→ 失業手当は、原則28日ごとにまとめて支給されるため、
1回の支給額:4,000円 × 28日 ≒ 約112,000円



実際の支給額は、年齢や雇用保険加入期間、退職理由によって上下します。
失業手当はいつまで受け取れる?|支給期間の目安と延長の条件
失業手当がもらえる期間(=所定給付日数)は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって異なります。
とくに「会社都合」の場合は、自己都合よりも長く支給される傾向があります。
所定給付日数の目安|退職理由・年齢・加入年数で決まる
| 離職理由 | 被保険者期間 | 所定給付日数 〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合退職 | 10年未満 | 90日 | |||
| 10年以上 | 120日 | ||||
| 会社都合退職 | 1年未満 | 90日 | 90日 | ||
| 1〜5年未満 | 180日 | 150日 | |||
| 5〜10年未満 | 120日 | 210日 | 240日 | 180日 | |
| 10〜20年未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 210日 | |
| 20年以上 | 210日 | 270日 | 330日 | 240日 | |
※ 就職困難者(障害者、高年齢者など)の場合はさらに長くなる場合があります。
給付期間はいつからいつまで?【原則1年、最大3年の猶予】
失業手当の受給には「期限」があります。
原則として、離職日の翌日から1年以内にすべての手当を受け取り終える必要があります。
ただし、すぐに就職活動ができない特別な事情がある場合は、ハローワークに申請することで、受給期間の“猶予”を最大3年間まで延ばすことが可能です。
*「3年間もらえる」ではなく、受給の“猶予期間”が最大3年に延びるという意味です。
延長が認められる主なケース
- 妊娠・出産
- 病気・けが
- 介護(家族の看護など)
- 災害や交通事故などによる就職困難
- 就職困難者(高齢者、シングルマザー等)



「体調が悪くて、すぐに活動できない…」
そんなときは、あきらめずにハローワークで相談を。
受給期間を最大3年まで延ばせる制度が使えることもありますよ。
延長申請の注意点
- 申請は、離職日の翌日から30日以内に行う必要があります
- ハローワークで「受給期間延長申請書」を提出します
失業手当以外にもある!知っておきたい支援制度
再就職手当|早めに仕事が決まった人に支給されるボーナス
失業手当の受給期間を残した状態で就職すると、「再就職手当」が支給されることがあります。
これは、残りの失業手当の一部をまとめてもらえる制度で、早く仕事が決まった人への“ボーナス”のようなものです。
支給される条件(一例)
- 雇用保険の加入期間が1年以上ある
- 待期期間(7日間)終了後に再就職している
- 1年以上の雇用が見込まれる(派遣・パートも対象)
- 元の勤務先に戻る再雇用ではない など
たとえば、90日分の手当のうち60日分を残して再就職した場合、約40日分前後の手当を一括で受け取れることもあります。



申請はハローワークで行います。
内定が決まったら、すぐに相談することが大切です。
※「再就職手当の条件・金額・注意点」については、今後くわしくまとめた記事を公開予定です。
公開後にリンクを追加します。
職業訓練|手当をもらいながら無料でスキルアップ
失業中にスキルを身につけたい人向けに、ハローワークでは「公共職業訓練」や「求職者支援訓練」という制度があります。
多くの講座が受講無料で、一定条件を満たせば交通費や手当(訓練延長給付)も支給されます。
受講中も以下の手当が対象になることがあります
- 通所手当(交通費)
- 受講手当(月1〜2万円程度)
- 失業手当の延長支給(訓練延長給付)
- 職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)※支給条件あり
受講にはハローワークの選考がありますが、主婦・ブランクがある方・未経験者も歓迎される講座が多くあります。



私も以前、職業訓練を受けたことがあります。
無料で学びながら手当ももらえて、久しぶりの勉強も楽しく感じられました。
※「職業訓練」については、今後くわしくまとめた記事を公開予定です。公開後にリンクを追加します。
失業手当をもらいながら扶養に入れる?|健康保険と税法上の違いに注意
失業手当を受け取りながら、配偶者の扶養に入れるのかどうか。
これは「健康保険の扶養」と「税法上の扶養」で判断基準が異なります。
健康保険の扶養:失業手当も収入としてカウントされる
健康保険の扶養に入るには、年収が130万円未満であることが条件になります。
この「年収」には、失業手当の金額も含まれます。
たとえば、失業手当の1日あたりの金額が3,611円を超えると、1年間でもらう金額が130万円を超える計算になります。
計算例:3,611円 × 30日 × 12か月 = 約130万円
ほとんどの方は、3,611円を超えることが多いため、支給が終わったあとに扶養に入る流れになるのが一般的です。
失業手当を受給している間は、配偶者の健康保険の扶養に入ることができず、一時的に国民健康保険にするなどして、自分で保険料を支払う必要があります。



扶養に入るときに夫の会社から「失業手当を受給していないか」を確認され、受給中は扶養に入れないと説明されました。
今回も同じで、今は失業手当をもらっているため、自分で国民健康保険に加入しています。
ただし、健康保険の判断基準は、加入している保険組合によって少しずつ違うことがあります。
- 1日あたりの失業手当の金額が3,611円を下回っている
- 支給期間がごく短期間で、年収換算しても130万円未満になる
の場合は、扶養に入れる可能性もあります。
必ず配偶者の勤務先や加入先の保険組合に確認しておきましょう。
税法上の扶養:失業手当は非課税なので扶養に入れる
税法上の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)の判定では、失業手当は非課税扱いとなり、収入に含まれません。
- 失業手当を受けていても、ほかの収入(アルバイトなど)が103万円以下であれば、配偶者控除の対象になります
ポイント整理|税金の扶養と健康保険の扶養はちがう!
失業手当をもらっている間は、
- 税金の扶養(配偶者控除など)には入れることが多い
- 健康保険の扶養には入れないことが多い
このため、自分で国民健康保険に入って、保険料を払う必要があるケースが多くなります。
失業手当を日額4,000円もらっている場合
税金の扶養(配偶者控除など)
- 失業手当は「非課税」だから収入にカウントされない
- 所得が103万円以下なら、夫の扶養となり税金の控除対象になる
健康保険の扶養
- 日額が3,611円を超えているので、健康保険の扶養には入れない
- 自分で国民健康保険に加入し、保険料を払う必要がある
失業手当のよくある質問|Q&A形式でやさしく解説
- 主婦でも失業手当はもらえますか?
-
はい。条件を満たしていれば主婦でも受給できます。
ポイントは、次の3つです。
- 雇用保険に加入していた(週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み)
- 退職前の2年間に、月11日以上働いた月が12か月以上ある(自己都合退職の場合)
- 退職後も就職の意思と能力がある(子育て中でも「すぐ働ける」状態)
これらを満たしていれば、主婦でも失業手当の対象になります。
- 失業手当はいくらもらえますか?
-
退職前にどのくらいの収入があったかによって、もらえる金額が決まります。
たとえば月20万円ほどの収入があった人なら、月10〜11万円台くらいが目安です。
これは、退職前の平均月収や年齢によって異なりますが、一般的には「退職前の賃金の50〜80%」が1日あたりの支給額として計算されます。詳しくは「雇用保険受給資格者証」で確認できます。
- 自己都合退職でももらえますか?
-
はい。自己都合で退職した場合でも、失業手当は受け取れます。
ただし、すぐには支給されず、「給付制限」という待機期間があります。通常は7日間の待期期間に加えて、2か月(※以前は3か月)の給付制限があるため、実際にお金が振り込まれるのは退職からかなり後になります。
なお、特別な事情があると1か月に短縮されるケースもありますが、これはかなり例外的です。
- バイトや在宅ワークをしても手当はもらえますか?
-
一定の条件を守れば、アルバイトや在宅ワークをしていても失業手当は受け取れます。
ただし、「働いたことを必ず申告すること」がルールです。
たとえ1日だけ・短時間でも、働いた内容と報酬額を「失業認定申告書」に記載しなければなりません。働いた日があると、その日は「失業状態」とは見なされず、手当の対象外になります。
とはいえ、バイトをした日数が少なければ、そのぶん減額されて支給されることもあります。うっかり申告しなかったり、過少に申告したりすると「不正受給」になるので、正直に申告することが大切です。
- 求職活動って、何をすれば実績として認められますか?
-
認定日までに、2回以上の求職活動が必要です(※初回は1回でOK)。
たとえば
- ハローワークでの職業相談
- 求人への応募
- セミナーや説明会への参加
などが対象です。
就職につながる行動であることが大切。わからないときは、ハローワークで確認しましょう。
まとめ|失業手当でもらえるお金と注意点をしっかり理解しよう
失業手当は、退職後すぐにもらえるものではなく、手続きや待機期間、給付制限などを経てようやく支給が始まります。
金額や受給期間は人によって異なり、申請のタイミングや働き方によっても変わるため、自分に当てはまるケースを事前に知っておくことが大切です。
退職前であれば、離職後のスケジュールをざっくり考えておくと安心ですし、手続きの流れを知っておけば、焦らずに動けます。
大切なのは、「知らなかった」では済まされないことが多いということ。
しっかり準備して、もらえるものはきちんと受け取りましょう。
私の体験談も、よければ参考にしてみてください。
ハローワークの雇用保険説明会へ|失業手当と職業訓練の話も聞いてきた